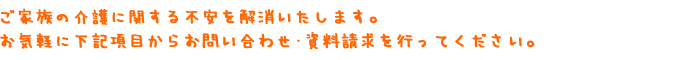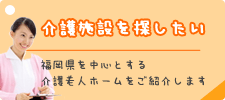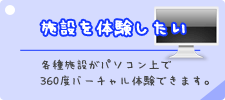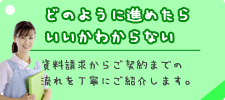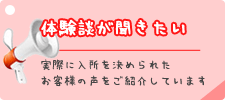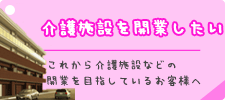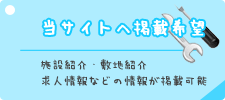高齢者の大動脈弁狭窄症 切開しない新治療法「TAVI」が普及|RME介護情報ねっと
高齢者の大動脈弁狭窄症 切開しない新治療法「TAVI」が普及 (2014-07-28)RME介護情報ねっと最新ニュースコラム
お電話・スマホからもお気軽にご連絡下さい。TEL092-481-1755、24時間365日受付中!お問い合わせはこちらから
HOME > 高齢者の大動脈弁狭窄症 切開しない新治療法「TAVI」が普及
高齢者の大動脈弁狭窄症 切開しない新治療法「TAVI」が普及

| ←前へ | ↑一覧へ | 次へ→ |

2014/07/28
心臓の大動脈の弁が固くなり、血液が流れにくくなって心不全などを起こす重症の大動脈弁狭窄(きょうさく)症の治療にカテーテルを使って人工弁を挿入する「経カテーテル的大動脈弁置換術(TAVI)」という新治療法が普及し始めている。高齢などで胸部の切開による外科手術が不可能な患者が対象で、患者の負担が少なく、短期間で退院できる。昨年10月には保険償還も認められ、実施病院は全国で30カ所以上に増えている。(坂口至徳)
QOLも改善
大動脈弁狭窄症は、収縮して血液を全身に送り出す左心室と大動脈の間にある大動脈弁に石灰が沈着して固くなり、十分に開かなくなる。65歳以上の高齢者の約4%に症状があると推計され、加齢とともに進行し、狭心症や失神、心不全などの症状が出れば生存率が低下する。
国内では毎年約7千人が病んだ大動脈弁を人工弁で置換する外科手術を受け、回復。しかし、ほぼ同数の患者が高齢や再手術不可能などの理由で外科手術が受けられず、症状が進行しているとみられる。TAVIはそのようなケースに有効で、これまで600例以上の手術が行われている。
国立循環器病研究センター(大阪府吹田市)の小林順二郎副院長によると、TAVIは2002年に欧州で開発され、改良を重ねてきた。人工弁は直径23~26ミリ。牛の心膜で作られた生体弁で、拍動で起きる血流によって開閉する。
治療はモニターを見ながら行う。太ももから血管内を通ってワイヤや風船を入れ、固くなった弁をこじ開けて広げる。その後、カテーテルの先に直径8ミリに圧縮した人工弁を付けて挿入。固くなった弁の内側に届いたところで、人工弁を風船で元の弁の大きさに膨らませ、外周を取り巻く金網状の金属で固定する。
80歳の男性は大動脈弁狭窄症で息切れなど狭心症などの症状が出て、同センターに入院。12年前に心臓の冠動脈の4カ所にバイパス手術を受けており、再度の外科手術はバイパス部分を傷付けて合併症が起こりやすいため、できなかった。
このため、小林副院長ら外科医と内科医がTAVIを行い、2時間で治療を終了。早期に回復した男性は1週間後に退院し、QOL(生活の質)も改善した。
◆体に楽な方法
ただ、この治療では弁が固まっているため、挿入した人工弁との間に隙間ができ、弁の周囲で血液の逆流が起きないようにぴったりと植え込む必要がある。カテーテル挿入の際にできた血栓による脳梗塞などにも注意が必要だ。その点を改良し、弁の周囲の金属部分に形状記憶合金を使って自動的に開くようにしたり、隙間を布で埋めたりする人工弁も開発され、一部は欧米で既に使われている。
TAVIが早くから行われてきたドイツやデンマーク、オランダでは保険での治療が認められるようになってから大動脈狭窄症の治療の半数近くに増えている。人工弁の耐久性についてはまだ開発されて間がないため、はっきりとした結論は出ていない。臨床例を見ながら年齢の適応を拡大していくという。
小林副院長は「今まで高齢で手術を諦めていた人もTAVIは人工心肺を使わないなど比較的、体に楽な方法なので治療を申し出


| ←前へ | ↑一覧へ | 次へ→ |