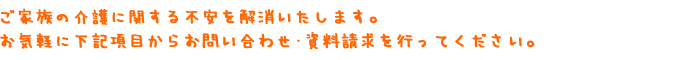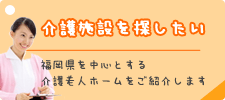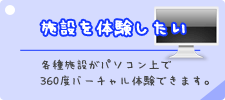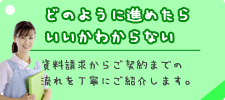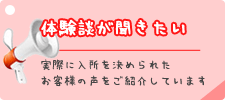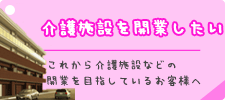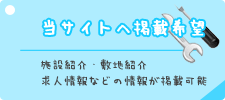熱中症に注意!!高齢者の「脱水防止」 水分と栄養管理で入院を回避|RME介護情報ねっと
熱中症に注意!!高齢者の「脱水防止」 水分と栄養管理で入院を回避 (2014-07-29)RME介護情報ねっと最新ニュースコラム
お電話・スマホからもお気軽にご連絡下さい。TEL092-481-1755、24時間365日受付中!お問い合わせはこちらから
HOME > 熱中症に注意!!高齢者の「脱水防止」 水分と栄養管理で入院を回避
熱中症に注意!!高齢者の「脱水防止」 水分と栄養管理で入院を回避

| ←前へ | ↑一覧へ | 次へ→ |

2014/07/29
毎日、酷暑が続いていますが、ニュースでも熱中症で搬送された人の多さを知らせています。
夏の水分補給は大事だと分かってはいても、特に 高齢者は「食べたがらない」「飲みたがらない」「むせてしまう」などで家族も困難を感じている。水分ばかりが注目されるが、高齢者は食が細った時点で黄信号。高齢者向け脱水予防のヒントをお届けする。(佐藤好美)
6月末、管理栄養士の米山久美子さんが、東京都目黒区の小島祥子さん(88)=仮名=宅を訪れた。小島さんは立ち上がりが困難で、食事や排泄(はいせつ)に介助が要る。要介護4の1人暮らしを、近隣に住む息子の誠さん(53)=同=と朝夕の訪問ヘルパーが支えている。
祥子さんはこの日、デイサービスから帰ると、夕食のオムライスを一さじ一さじ、口に運んだ。認知症の祥子さんが自分で食べるのは良い兆候。それを見て、米山さんは聴診器で飲み込みの音を確認。「食事、進みますね。ごろごろも聞こえないし」と安堵(あんど)した。日頃の食事内容や量、進み具合を聞き取って摂取カロリーを計算。体重を確認して、誠さんに「カロリーがやや少ないけれど、体重が横ばいだから安心していいと思います」と声を掛けた。
そのうえで、カロリーアップに朝の水分摂取時、高カロリードリンクを試すよう提案した。「暑くなるので、脱水にならないよう早めに対応したい。可能なら日中、ヘルパーさんに短時間入ってもらって水分補給ができるといいんですが…」
米山さんが祥子さんのケアマネジャーから「食事をしない利用者さんがいる」と相談を受けたのは3年前の夏。訪問した米山さんは、食事場所を変えて祥子さんの気分を引き立て、少量でカロリーが取れる栄養ゼリーを導入した。少し食が進むと、祥子さんの覚醒状態が良くなり、自分で食べるように。腎臓病や高血圧もあるため、塩分、タンパク質摂取に気をつけつつ、低栄養にならないよう心掛ける。
米山さんは「訪問すると、実際の食事や味を見て具体的なアドバイスができる。触れれば、むくみやかさつきも分かる。水分と栄養コントロールで入院を回避していきたい」と話している。
■食の細さも原因 自然に取る工夫を
脱水は水分の問題と思われがちだが、食が細るのも大きな原因。食事に含まれる水分は多いからだ。高齢者は慢性的に軽い脱水や低栄養の人が多く、ちょっとしたことが救急搬送につながりかねない。
だが、ペットボトルを置いておけば水を飲むというものではない。栄養・嚥下(えんげ)補助食品のメーカー「ニュートリー」が行った「高齢者の水分補給に関するアンケート」によると、「水分不足が不安」と考える介護専門職は95%に上るが、「難しい」の回答も93%。理由には、(1)本人が飲まない(30.1%)(2)飲ませようとしても拒否する(21.9%)(3)むせる(17.2%)-だった。
国立国際医療研究センター病院・リハビリテーション科の藤谷順子医長は、(1)食事に含まれる水分を軽視しない(2)自然に液体を取る工夫-を挙げる。「夏はそうめんやお茶漬けで済ませる人が多いが、ご飯とおかず、みそ汁の食事に比べると水分もカロリーも少ない。温泉卵を落とすとか、冷ややっこを足すとか、汁物を加えるなどの工夫をしてほしい」
食事と食事の間には水分摂取を勧めるだけでなく、一緒にお茶の時間を持ったり、お茶請けを用意するなど自然に飲める工夫がほしい。牛乳、乳酸菌飲料、野菜ジュースなど目先の変化も重要。スープやココアならカロリーも取れる。市販の経口補水液やゼリー飲料がおいしく飲めるときもある。
「むせ」が怖いときは、ネクターのようなトロリとした飲料が飲みやすい。また、ペットボトルのような底の深い容器はあごを上げないと飲めず、むせやすい。アサガオ型の浅めの湯のみがお勧めだ。
脱水で特に注意が必要なのは、(1)利尿剤を飲んでいる(2)認知症がある(3)下剤を飲んでいる(4)嚥下障害がある(5)糖尿病がある-などの人。夏と冬では必要な水分量も違う。心臓病や腎臓病で水分制限を受けている人はどの程度までは水分を取っていいのか、主治医に再確認したい。
水分以外で注意したいのは運動量の激減。藤谷医長は「夏場に外出を控えていると体力が落ちる。朝夕の涼しいときに歩くとか、屋内でテレビコマーシャルの数分間に椅子から立ったり座ったりするだけでも筋肉は鍛えられる。元気に秋を迎えてほしい」と話している。
■管理栄養士の訪問指導の利用も
管理栄養士の訪問指導は介護保険サービスの一つ。高齢者の栄養評価を行い、(1)栄養状態の改善(2)食事の形状や調理方法(3)食べる姿勢-などをアドバイスする。
日本在宅栄養管理学会(訪栄研)の前田佳予子理事長は「例えば、飲み込みが悪い場合、小さく切るだけでは逆に食べにくい。咀嚼(そしゃく)や嚥下の状態に合わせて食品をミキサーにかけて固めるのか、刻んでとろみをつけるのか、適した形状をアドバイスします」。
低栄養だと床ずれになりやすく、入院の可能性も高まる。食事指導に工夫が必要なのは、食べたり飲んだりするとむせる▽食べたり飲んだりしたがらない▽脱水や肺炎で入退院を繰り返す▽むくみがひどい▽下痢、便秘がひどい▽床ずれがある-などの人。
管理栄養士の訪問指導は浸透しておらず、地域も限定されるが、受けたい場合は主治医やケアマネジャーに相談する。都道府県の栄養ケアステーションに相談したり、訪栄研のホームページ(http://www.houeiken.jp/kensaku.html)で訪問栄養士を探す方法もある。
| ←前へ | ↑一覧へ | 次へ→ |