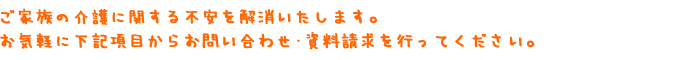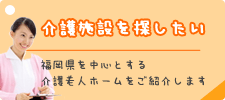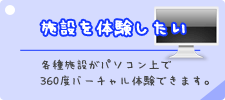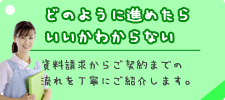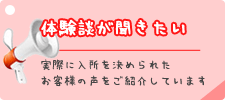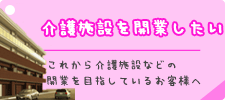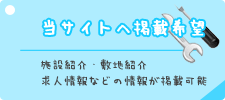ポリファーマシー「高齢者の薬の飲み過ぎ」問題!|RME介護情報ねっと
ポリファーマシー「高齢者の薬の飲み過ぎ」問題! (2017-08-28)RME介護情報ねっと最新ニュースコラム
お電話・スマホからもお気軽にご連絡下さい。TEL092-481-1755、24時間365日受付中!お問い合わせはこちらから
HOME > ポリファーマシー「高齢者の薬の飲み過ぎ」問題!
ポリファーマシー「高齢者の薬の飲み過ぎ」問題!

| ←前へ | ↑一覧へ | 次へ→ |
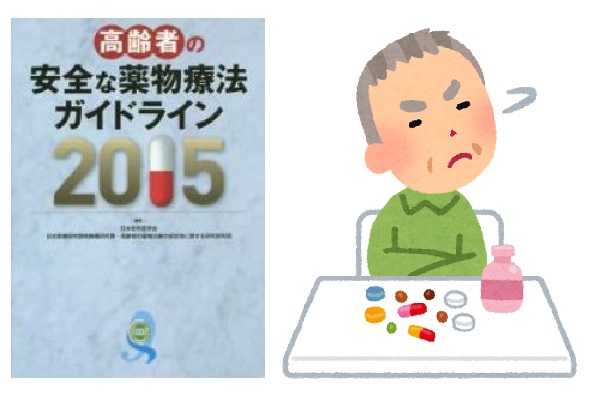
2017/08/28
高齢になると、複数の病気を患うことが多くなります。
そのため、何種類もの薬を処方されて飲むことになり、これを《ポリファーマシー》と言います。
ポリファーマシー(薬の飲み過ぎ)により、代謝が衰えて内蔵の働きも弱っている高齢者にとって大きな負担になります。
医療関係者の間でも、ポリファーマシー問題に関心を持ち、これを防いでいく取り組みがスタートしています。
厚生労働科学研究によると、65歳以上の高齢者700人を対象に、薬の他剤処方や飲み過ぎで起こった主な有害事象を調べると、1位が意識障害・低血糖・肝機能障害(いずれも9.6%)、2位が電解質異常(7.7%)、3位がふらつき・転倒(いずれも5.8%)だったそうです。
2014年12月、厚生労働省がある県の75歳以上の高齢者をデータ分析したところ、3割近い高齢者が、10種類以上の薬を飲んでいることが判明しました。
この中には、胃腸調整剤など成分や薬効がかぶっているものも多く含まれるので、副作用も心配されるので、注意が必要です。
ポリファーマシーに明確な基準はないようですが、6種類以上の薬剤を服用していると、有害事象が生じやすくなることや、5種類以上で転倒リスクが増すなどの報告を踏まえて、5~6種類以上をポリファーマシーの目安とするのが、妥当とされています。
日本老年医学会は、高齢者の安全な厄日津ガイドライン2015を作成し、特に慎重な投与を要する薬物のリストを策定しています、使用している薬が使用法の範囲内か、効果の有無はどうか、減量や中止は難しいか、代替薬はあるか、患者の同意は得られるか・・・などをチャートにして、『継続』・『使用の中止・減量』・『代替薬による継続』などの使用判定を行います。
ポリファーマシー対策では、薬剤師の積極的介入が重要となりますが、「ポリファーマシー対策=薬を減らす」ことではないそうです。
患者の病態や生活状況、患者の意向も含めて、本当に必要な薬剤を医師と協同で検討しながら、もっとも適切な薬物療法を実施していくことがポリファーマシー対策になるとのことです。
参考:慢性期・回復期における病棟薬剤業務セミナー「高齢者におけるポリファーマシー対策について」・厚生労働省
| ←前へ | ↑一覧へ | 次へ→ |